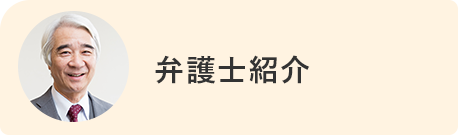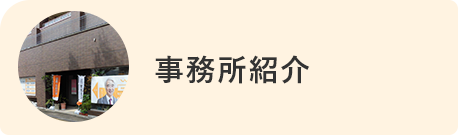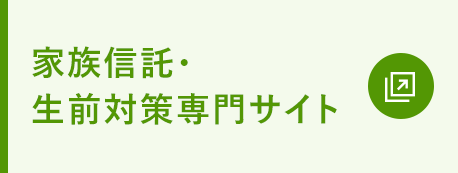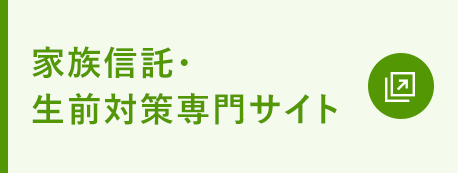リーガルタイム
-
- 2018.06.07
- 2018/6/7【さい帯血転売で有罪判決】
-
- 2018.04.26
- 2018/4/26 【児童の列と車が衝突するも,高裁が無罪判決】
-
- 2018.04.26
- 2018/4/26【だまされたふり作戦で、受け子に詐欺未遂罪が成立】
-
- 2018.02.28
- 2018/2/28【民法という法律の改正について―配偶者居住権って?】
-
- 2018.02.28
- 2018/2/28【民法という法律の改正について―遺言に関する新たな制度】
-
- 2018.02.15
- 2018/2/15【女子生徒の黒髪強制について】
-
- 2018.01.29
- 2018/1/29【マンション管理組合理事長】
-
- 2018.01.24
- 2018/1/24【長時間労働とうつ病】
-
- 2018.01.12
- 2018/1/24【長時間労働と脳・心臓疾患】